就業規則・給与規程・関連諸規程の作成、改正、運用相談/適正労働時間管理
□
□働き方改革実行の就業規則と関連労働法規への対応 □
 ◆就業規則・給与規程・退職金規程・育児介護規程等の作成・変更・改正
◆就業規則・給与規程・退職金規程・育児介護規程等の作成・変更・改正
◆雇用関係の開始から終了まで
◆関連法規の改正、新設に対応した整備が行われていますか
◆労働契約法・パートタイム労働法への対応
◆ 労働時間とはどんな時間
社会経済環境の変化、法改正及び企業の実状に合った就業規則等の作成・改正・運用が行われていますか
◆「就業規則」改正に兼業・副業もOK (厚労省モデル就業規則の改正へ)
CSRによる組織統治、人権、労働慣行・・
就業規則の作成例 ダウンロード版 東京労働局 一括届出制度 リーフレット チェックリスト 東京都産業労働局
¶労働契約を結び組織の一員となり就労しますと、合理的な労働条件が定められている就業規則が事業所内に掲出され,いつ誰にも周知されているような状態であれば労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によります。 (労働契約法第7条)
¶ 行政通達等を根拠とした就業規則 ● リスクマネージメント ● コンプライアンス遵守の
¶ 豊富な体験と紛争解決手続代理業務(特定社労士)の実績で企業経営をフルサポートいたします。
¶ 労基署の是正勧告にも、事前のリスク回避、事後の最善な解決策などのベストなご提案で対応します。
時季指定に関する就業規則の規定例
厚労省が「モデル就業規則」の改正案を有識者検討会に提示 2017年11月20日
現在のモデル就業規則では原則禁止としているが、事前届け出を行うことを前提に副業できると明記した。
現在は「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」としている規定例を削除し、「労働者は勤務時間外において他の会社等の業務に従事することができる」と明記。
・政府の働き方改革実行計画では、副業・兼業の推進を掲げている。指針案では企業が労働者の自己申告に基づいて就業時間を把握し、長時間労働の抑制や健康管理に努める方向性を示してはいる。しかし、指針案に対し、本業と副業を合わせ長時間労働が生じる問題、企業が労働時間を管理することが不可能なこと、安全確保面での企業責任の所在、また社会保険、労働保険の適用・給付の問題など現行労働法制での未整理・不明確な課題の解決も残されている。 2017/11/21 日経
企業の事業領域にとらわれず社外人材との交流を促進し、優秀な人材を確保するため就業時間中でも、正社員・入社年数などの一定条件及び自社の業務への影響や利益相反関係のないという条件を付け、業務内容を事前に申請し承認されると、月間で定められた時間内なら他社での副業を認めている企業も既にある。
厚労省・東京労働局のモデル就業規則の服務規律 遵守事項 第11条⑥では、 「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」 と規定している。働き方改革の一環として、中小企業にも兼業・副業を後押しするため、その規則例を改正する方針である。 2016/ 11/23日経新聞
中小企業庁の「平成26年度兼業・副業に係る取組み実態調査事業報告書」によると、副業・兼業を許可している企業は全体の3.8%で大半は情報通信業であった。容認企業では、ビジネスチャンスの拡大、社員の成長・育成のメリットを挙げている。その反面、懸念企業では 労災事故への対応・会社業績への不安を煽っていると判断されるなどの雇用リスクへの回答があった。 2016/ 中小企業庁調査事業報告書
 |
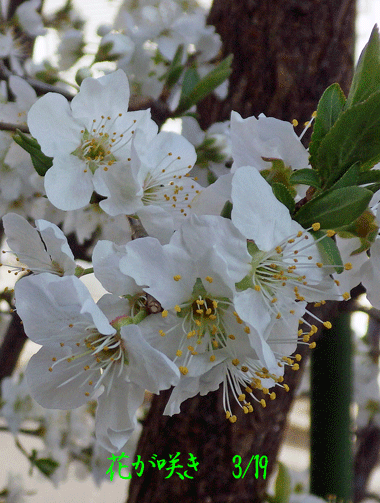 |
 |
 |
■マタハラ防止策 企業に義務化 就業規則への規定 相談窓口の設置 社員研修の実施 違反企業名の公表など
■改正道路交通法の一部が平成27年6月1日施行されました。
① 一定の病気・病状等に係る運転者を的確に把握するための整備、医師による任意の届出制度、暫定的な運転停止規定の整備など、懲役・罰金等の罰則規定が盛り込まれました。
② 自転車運転者講習に関する規定の整備・・・2 回以上摘発された悪質自転車運転者に対する受講命令・・・違反者に対する罰則規定 の整備などです。
このように自動車運転規程、自転車利用の通勤者に関する規程等の見直しも必要です。

■東京労働局定期監督結果取りまとめ 平成25年度における労働基準法・労働安全衛生法に関する主要な法違反の事例発表5/30
■時間外労働・休日労働・割増賃金率の状況調査 (平成25年4月1日時点)・・・労働条件分科会が10月30日に調査結果資料を配布
この調査は、平成17年度にも実施されている。今回は裁量労働制導入事業場を優先選定し監督官が訪問調査したもの。調査結果の詳細については次の PDF に示されているが、時間外・休日労使協定(36協定)を締結していなかった事業場の割合が多かった。
レポートはこちら
 |
 |
 |
 i i |
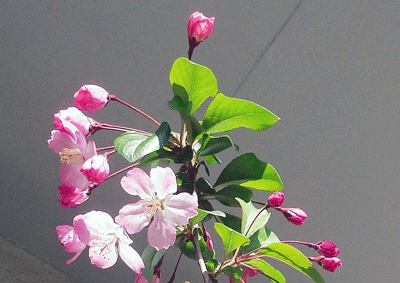 |
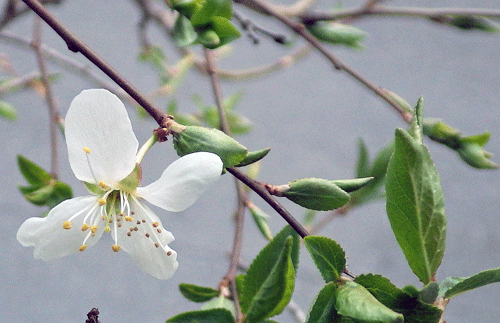 |
 |
 |
■年次有給休暇の計画的付与・・・有給休暇付与日数のうち、5日を除いた日数については、労使協定により休暇取得日を計画的に割り振ることができます。
夏季休暇、季節的繁閑、交替付与、個人の事情等と組み合わせて計画的に連続休暇を取得することができます。
◆FD (フロッピーデイスク)等による就業規則の届出ができなくなりした。
FDによる就業規則及び寄宿舎規則の受付が労働基準監督署で2013年4月26日をもって終了しました。4/27以降は電子媒体による届出にはCD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RWなどにより所定の要件を満たしたものによるによる必要があります。
なお、添付する意見書、同意書等は書類での届出が必要となります。 (2013/4/27)
詳細については厚労省の次のPDFを参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/130418-1.pdf へのリンク
企業経営と就業規則
 |
危機管理 ⇔ BCP策定 ⇒有事への対応 |
2009年5月の弱毒性新型インフルエンザの影響を受けて、新たに対策を作成した企業も多く、出張禁止、自宅待機などの対策も講じられました。
強毒性新型インフルエンザの流行で想定される欠勤や自宅待機への具体的対応などは、かなり進んできてはいるようです。
食中毒、パンデミック、製造物責任・・・脅威への事前対策が必要です。
手洗い・うがいなど、従業員や家族への感染予防策の指導、申告ルール化、健康管理・出退勤の適切な管理・運営など、国、行政だけでなく、地域とともに企業にもその対策を講ずることが求められています。 |
 |
就業規則とは何か
企業で働くうえで労使の最低限の就業条件を定めたものが就業規則といえます。
しかし近時、企業を取り巻く経営環境が激変しております。個人情報保護の取り扱い、うつ病などの健康管理、パワハラ、セクハラ問題の増加、「問題社員」の増加、ワークシェアリング、企業情報漏洩防止などなど・・・・。
うつ病等の再発に対する休業規定の見直し、ハラスメント問題への防止策・対応策、適切な事後処理対応、使用者責任、職場環境配慮義務違反、不法行為責任、信用失墜、損害賠償責任、人材の流失など様々なリスクがあります。
個別企業の実態に対応した内容を明記し、整備・周知・管理しておくことです。
個別労使紛争も多発しており、企業経営を取り巻く環境には様々なリスクが存在し、事前に予測して回避するための対策及び事後リスクヘッジなど、緊急事態を未然に防止する仕組みを構築する必要があります。
平成22年4月1日から改正労基法が施行されました。長時間労働を抑制し、仕事と生活の調和のとれたワーク・ライフ・バランス社会の実現を目指して、労働時間に係る制度の見直し等が行われました。時間外労働の割増賃金率が引き上げられました。
就業規則は企業の健全な発展のために必要不可欠なもの コンプライアンス(法令遵守と倫理遵守)
企業は、その経営理念と経営方針に沿って就業ルールを作成し、従業員は、その規則を遵守し、企業目的の遂行に努力する。 始業・終業時刻の変更・・・・・就業規則を変更します。 |
  |
※2012年度(12/4~13/3)コンプライアンス違反を倒産理由とした「企業の倒産動向調査」によるとコンプライアンス違
反を倒産理由の一因とした倒産企業数は200社で調査を開始した05年度以降過去最多を更新した。「雇用」面においても11件と過去最多を記録している。
社歴30年以上の老舗企業や名門企業でもコンプラ違反で倒産しており、特に目立つのは運輸業の「業法違反」、業種では建設業が最多となっている。ツアーバス事件など、無理な人員配置による道交法・法令順守を欠いた違法な運行管理などによる業法違反事故以来監査強化による運輸業などへの監査が厳格化している。
コンプライアンス経営への意識が高まっている反面、法令違反で告発される企業も後を絶たない。 資料 5/28
管理職と残業手当
労基法では「監督若しくは管理の地位にある者には労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」と定めています。(但し、深夜業及び年休に関しては適用されることになる) |
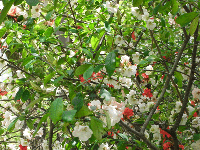 6月、各地に心なごますきれいな 花々が咲き誇っています |
従来の判決例をみると、管理監督者性は容易には認められない傾向にあります。
平成20年1月28日のマックの判決でも同じことが言われています。
それではどうしたらよいのか? 制度変更するのか? 過去分はどうするのか? 精算するのか? 示談にするのか? 裁判にするのか?控訴するのか? 職務権限を減らして残業手当の支給対象者にするのか? 残業を付ける方法はどうするのか?
名ばかり管理職対策へのご相談が増えてきております。
監督署からの是正勧告を受ける前に対応策を講じて置きましょう。
※多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について~具体的な判断要素を整理した通達~
※同上 管理監督者についてのQ&A
「就業規則」と「労働契約」とは根本的に異なる別個の法制度であります。労基法2条2項が、労使双方に労働協約、労働契約と並んで就業規則の遵守義務、誠実履行義務を明言し、行政当局が、労基法15条の労働条件明示義務にいう「明示」は就業規則の明示で足りるとの通達を発していることは(昭和29・6・29基発355号)就業規則の労働条件設定が法制度上のそれであるかのような印象を与えています。 |
.jpg) |
就業規則についての法的性質論には、法規範説、契約説及び事実規範説などがあり、それぞれの立場に立つ判例がみられるが、秋北バス事件判決(昭和43年12月最高裁大法廷)で、個別的な労働契約における労働条件の決定は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、一種の社会的規範としての性質を有するだけでなく、それが合理的な労働条件を定めている限り、法的規範性が認められるとしています。
就業規則の法規制の歴史と政策
明治初期の就業規則・・・日本が殖産興業の国是のもとに開設した官営工場には、集団的雇用管理の手段としての就業の秩序と規律を遵守させるための命令規則がありました。 |
 |
大正15年法制は、「職工ノ就業ニ関スル諸条件之ニ関スル規律ノ内容ヲ明ニシテ之ヲ職工ニ了知セシメ工場作業ノ進行ノ円満ヲ期セムトスルモノ」(工場法施行令)つまり就業条件、規律事項を明確化した就業規則の作成を義務付け、行政官庁への届出、変更命令のもとにその内容の適正化を図るというものでした。
就業規則と現行労基法
昭和22(1947)年制定の現行労基法は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に、労働時間制度、賃金の決定、計算方法、退職に関する事項等の集団的、統一的な労働条件内容を明記する就業規則の作成を罰則をもって義務付けています。(89条、120条)
新たに使用者に就業規則作成・変更時の過半数労働者代表の意見聴取義務を課し(90条)、労働契約に対する最低労働条件保障的効力を規定しました。(93条)
その目的・趣旨はなんであったのか。一般的には、労働条件の客観化・明確化による労働者利益擁護のための、労使の私的自治⇒契約関係への国家による後見的介入のための法システムといえましょう。
◆労働条件決定の基本原則は労使対等決定原則(2条1項) 月日
月日
「労働契約法」
改正労働契約法が2012/8/3成立・・・「雇止め法理」の法定化は平成24年
8月10日から施行、 「無期労働契約への転換」と「不合理な労働条件の禁止」
は平成25年4月1日から施行されている。
 |
 |
 |
| プラム(スモモ)の樹 実の表面のブルーム感がグー 果実は暗紫色で豊かな甘味 (2015/06/21 shoot) |
改正のポイント
・対象となる契約は、法施行後に契約社員、パート、派遣社員が締結する新規契約や更新契約が対象となる。→法施行直後に雇用された人の勤務期間が5年を超える2018年度から影響が出てくる。
・期間を定めない雇用に転換する場合には、企業は原則、賃金・勤務時間などの労働条件の調整が必要となるが、特に別の取り決めがない限り、賃金などの労働条件は有期雇用のときと変わらない。
・6カ月以上の空白期間を置くと、通算期間がリセットされゼロになる。
(2012/8/4)
◆「雇止め法理」の法定化は平成24年8月10日施行
近時、就業形態の多様化により雇用・労働関係を取り巻く状況の変化に伴い、労働条件の小グループ化や労働条件の変更の増加が見られるが、解雇に係る紛争や条件引下げに係る紛争を始め個別労働労働関係紛争が増加しています。
平成20年3月1日に施行された「労働契約法」では望ましい労働契約の労使のあり方を事業主と労働者の双方に周知し、円満かつ適正な労使関係を構築し、紛争を未然に防ごうとしています。
その基本的考え方は、就業規則をめぐるルール等を明確にすること
1.就業規則と個別労働契約の関係の明確化(合意成立の推定の必要)
2.就業規則を変更する際のルールの明確化(変更の合意成立の推定の必要)
3.就業規則の必要記載事項の追加(転居を伴う配転・出向、休職・懲戒事由等)
4.契約締結時の明示事項の追加(転居を伴う配転・出向)書面による明示方法
5.採用内定取消,試用期間中の解雇へのルール適用
6.懲戒等の根拠条文(濫用法理の設定)
7.その他労働契約終了場面でのルールの明確化(解雇、解雇の金銭的解決等)
就業形態の多様化と就業規則
|
就業形態の多様化に伴い、正規雇用の割合が低下し、パート、アルバイト、派遣労働者、契約社員、嘱託社員など 様々な名称を持つ非正規雇用が増加しています。特に、週35時間以上のフルタイム者と変化ない非正規の従業員が増加しています(派遣・契約・嘱託)。製造業における請負労働者としての従事者も増加しています。非正規雇用によるコスト抑制も行われています。適用範囲を区分した規定の作成も必要です。  |
賃金規程・退職金規程
労基法89条には「賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項」について作成し、変更した場合においても行政官庁に届出しなければならないとあります。又、同法11条には「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」
と定義しており、就業規則、労働契約、労働協約により、予め支給条件が明確である場合の退職手当も賃金である。
1980年代の円熟した「能力主義」賃金制度に代り、90年代以降経済環境の激変から日本の賃金制度は「成果主義」賃金制度が追求されてきました。能力と成果は因果関係があって企業は従業員の能力開発を図り、能力を活用しながら「成果」を上げていかねばならないということでした。
要約すると、職務遂行能力(職能資格等級)から役割(役割等級)へと変化し、仕事の結果を評価して支払われる賃金でした。
多様化した就業形態に対応した就業規則、賃金規程の適用や柔軟な運用が求められています。
改正高年齢者雇用安定法により、定年年齢の引き上げ、継続雇用制度の導入や再雇用契約、適格年金や厚生年金基金の廃止、新企業年金制度の採用(DC,DB)などによる退職金制度、労働条件の改正、切り下げなど企業経営を取り巻く課題は山積しています。過去の判例を評価・吟味して高度の必要性、合理性を有し、かつ必要な手順を踏んだ拘束力を持ち得る就業規則や賃金規定の改正が肝心です。退職金制度も年功的なものから能力主義や成果主義制度の退職金制度に移行すべきでしょう。
 |
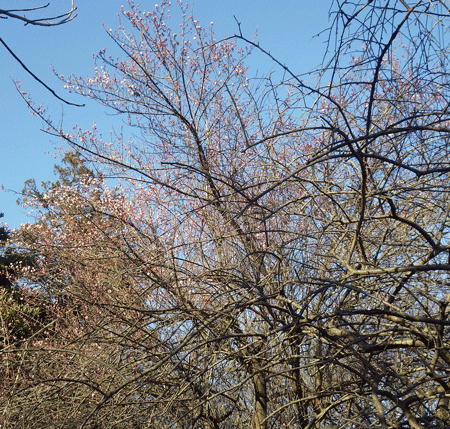 |
 |
Spring is here マンサク ウメ ツバキ (3カットとも 2017年早春 2月 埼玉県営 和光樹林公園にて)
![]()
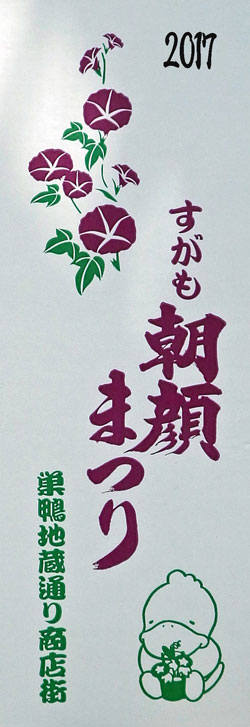 |
 |
 |
 |
 |
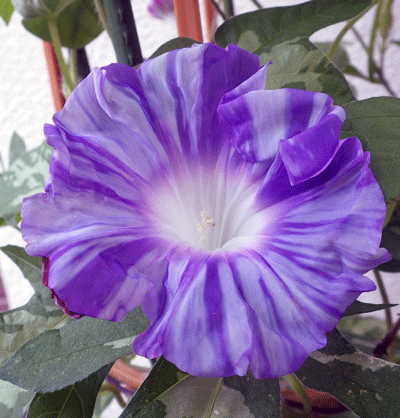 |
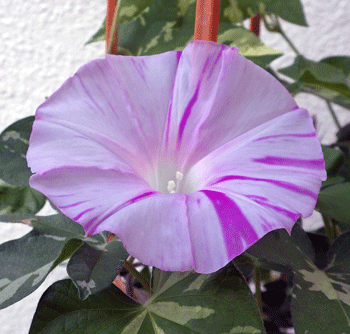 |
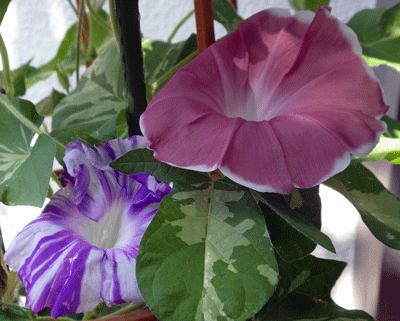 |
Summer is here アサガオ 2017 7月初旬~8月初旬

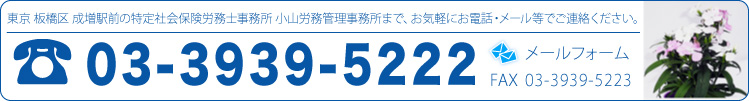

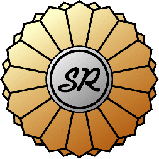
.jpg)
JAPHIC.jpg)
.png) お問合わせはこちら
お問合わせはこちら