確定拠出年金(DC)401K・確定給付(DB)企業年金
■改正確定拠出年金法(平成28年6月3日公布)の改正事項のうち、平成29年1月1日施行分に関する政令が9月23日、省令は10月5日に公布されました。
脱退一時金の支給要件の加入者資格喪失時の加入者期間と資産額jが、「3年以下又は25万円以下」になっています。
詳細は ⇒ 平成29年1月実施の改正事項に関する政省令の公布
これまでは自営業者や企業年金がない一部の会社員に限られていた「個人型」に、主婦や公務員が加入できるようになった。既に企業年金に加入している会社員も併用して利用できるようになる。 基本的に国民すべての人が加入適用対象者となる。
中小企業向けに、「簡易型」制度も新設され新規設立が簡易化され、「小規模事業主掛金納付制度」(マッチング拠出)も創設された。
DCの拠出規制も月単位から年単位へと変わった。
DCの加入者は現在、約500万人(そのうち「個人型」は約21万人)と伸び悩んでいるが、あるシンクタンクの予測によると公務員だけでも400万人位が個人型に加入すると見込んでいる。その資金流入額は年4800億円と予測している。
制度の拡充により株式投資への拡大も期待されており、厚労省もNISA並みの加入(約1000万人)を目指したいという。
それに伴い金融機関などは既に今回の制度改正を見据えセミナーを開設したり、相談体制などの営業活動を強化し顧客開拓に力を入れてきている。
超低金利が長引き、貸出金利収益に期待できない中、加入時に加え年間手数料収入が稼げる分野に力を入れている。
改正確定拠出年金法
í 個人型確定拠出年金の愛称が 「iDeCo(イデコ)」 に決定
■平成28年1月から実施される確定拠出年金(DC)制度の普及、推進にあたり、実施主体者である国民年金基金連合会と制度の担い手である金融機関、生・損保、信託、証券等が連携し、改正の円滑な実施のための広報啓発及び制度周知活用の推進を目的に、「確定拠出年金普及・推進協議会」が設置され、愛称募集が8/1から8/21まで行われ、応募4,351件の中から9月16日に、「 iDeCo イデコ 」に決定された。
英語表記は individual-type Defined Contribution pension plan からとったもので、 i は「私」=自分で運用する年金を表記したもの
詳細は、http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000136983.html を参照
平成26年度税制改正で、企業型確定拠出年金加入者の拠出限度額が平成26年10月1日から次のように引上げられました。
① 他の企業年金がない場合・・・・・企業の拠出金上限月額 5万5000円
マッチング掛金(従業員の上乗せ拠出)・・・・・企業の掛け金の額以下で2万7500円以下)
② 他の企業年金がある場合・・・ 企業の拠出金上限月額 2万7500円
DC(確定拠出年金)は平成13年10月に導入され、厚労省によると、平成24年3月末で18000社を超え、加入者464万人で
そのうちマッチング拠出制度が始まった平成24年1月以降、制度の利用者が増え続け、DC導入企業の2割、約3800社で実施しているという。
なお、個人型確定拠出年金の掛金限度額の引上げは見送られており、第1号加入者68000円、第2号加入者23,000円は変わっていません。 ⇒確定拠出年金制度について


気仙沼 落合直文 煙雲館庭園 震災から1年3か月後の2012年6月下旬の夕暮れ方 煙雲館庭園から気仙沼湾を臨む
平成26年度厚生労働省関係税制改正について
◆私的年金制度・退職金制度について
増えた選択肢にどう取組みましたか
これからどれに移行しますか
| 現在の企業年金を継続(厚生年金基金・適格年金) | 新企業年金へ移行 DC、DB(規約型・基金型) | ||||
| 確定拠出年金DC(日本版401K) | |||||
| 混合型年金CB(キャシュバランス) | |||||
| 年金制度の廃止 | |||||
| 自社年金 | 中退金 | 特退金 | |||
| 退職一時金 | 退職金前払制度(一部・全部) | ||||
→ 移行パターン
→ 制度の組合わせと割合
→ 資産移管
→ 掛金設定
退職給付制度と退職給付債務
2001年3月期に退職給付に係わる新しい会計基準が導入され、すべての退職給付制度について退職給付債務=PBO(市場金利の割引率により時価評価した負債)及び退職給付費用の内訳等を財務諸表に注記として開示反映させることが義務づけられた。 |
 |
従来の退職給付制度
企業年金(厚生年金基金・適格退職年金)
退職一時金制度(引当金等による社内準備)
中小企業退職金共済制度
特定退職金共済制度(建設業・清酒製造業・林業退職金共済制度)
その他
新しい年金制度の登場と適格退職年金の廃止
確定拠出年金(DC) 2001年(平成13年)10月
確定給付企業年金(DB) 2002年(平成14年)4月
厚生年金基金の代行返上(将来分2002年4月、過去分2003年9月)
適格年金の廃止 (1962年にスタートした適年は50歳の誕生日にあたる2012年4月をもって移行期間が終了しました)
環境変化
雇用形態の多様化
公的年金の改正(2000年、04年)、支給開始年齢の引上げ・・・2025年65歳支給
基金運営の弾力化措置・・・DBの政省令、法整備される
運用リスクの顕在化
無税引当金の廃止
成果主義の浸透(年俸制・ポイント退職金)
税制適格年金から混合型への移行⇒選択肢の拡大
バブル崩壊後の株価低迷で、DB(確定給付型年金)を採用する企業は予定利率を下回った分の穴埋めを迫られている。 |
 まんさく・・・春にまず咲く 2月18日 和光市樹林公園にて |
適年廃止と他年金への移行状況
中小企業を中心に普及していた適格年金は2012年3月末をもって廃止されました。適年からの移行先はおおむねDB2、DC1、中退共3、その他多くは解散4となっており、4割の企業は企業年金を持つことをやめた。
2013年2月1日の社会保障審議会有識者専門委員会でも、中小向け年金制度の創設について議論は深まらなかった。
DBの規約型が適年からの移行を吸収し設立件数が伸びている。2011年6月1日現在1万331件、基金型331件、DB加入者数727万人(2011年3月末)となっている。
企業型DC加入者数は400万6000人となっている。
※09年1月に「適格退職年金の企業年金への移行支援本部」が発足し、次のような規制緩和が実施された。
①企業ごとの個別資産管理が可能になった。
②障害・遺族給付金の基準額が改正された。
③給付額の算定方法設計の明確化、弾力化が行われた。
同本部は、2012年3月末まで方針未定事業所の適年対策に取り組んできた。

企業年金の新たな動向
2004年年金制度改正による企業年金分野での主な改正は
1 厚生年金基金の改正
2 企業年金(DC及びDB)の利便性の改正の2点です。
1 厚生年金基金関係
① 免除保険料率の凍結解除・・・・・
2.4%~3.0%(平均2.7%)⇒2.4%~5.0%(平均3.7 %)へと実質的に引き上げられた。 (2005年4月施行)
この結果基金の収入は1.4倍に増加し、財政運営が比較的楽になった。その反面、厚生年金本体の予定利率の引下げ(年5.5%⇒3.2%)に伴い発生するはずの最低責任準備金の増大は制度的に抑えられることになった。
② 離婚時分割の基金からの徴収額の計算・手続きの決定・・・・・
厚生年金本体に関して離婚時の年金分割がスタートしたことに伴い、分割を受ける者への給付必要額について国が報酬比例部分を代行する基金から徴収する額の計算式、手続きなどが決められた。 (2007年4月施行)
③ 企業年金の財政検証についての弾力化措置を対応策とした改正 ・・・・・
基金の運用環境の低迷により基金財政が悪化しており、その対策として積立金不足解消のための追加掛金の拠出を最大2年間猶予する。一定基準までの不足額は解消しなくてもよいというルールの導入。追加掛金算定にあたり、直近の利率を用いて計算できるように改める等
厚生年金基金制度10年(2023年)で廃止か? 健全性を条件に一部存続で調整も?
◇ 社会保障審議会の委員会は2013年2月1日、厚生年金基金制度は「廃止が妥当」との意見書をまとめた。意見書は、基金を5年以内に解散させ、10年間で代行制度を廃止するという厚労省試案の方向性は妥当とした。 財政難の基金には解散を促し、健全な基金には他の企業年金への移行を後押しする。 厚労省は意見書を受け、4月にも国会に制度改革法案を提出する予定。 一方、自民党の一部には一律廃止に反対する声もあり、意見書でも一定の基準を満たす基金は存続してもよいという意見もある。 基金のなかでも廃止に反対する基金、早期解散に賛成する基金とあり評価は分かれる。だが、存続が認められても、認可基準は厳しく存続する基金はほとんどない見通し。 2/13の自公厚労部会を受けて厚労省は試案をたたき台に法案作成に入っている。 しかし、厚労省の試算によると、2年後に代行割れとなるリスクのない基金は49基金(570基金中)しかなく、厚労省は実質制度廃止の方向での調整を図るようである。 但し、意見書では解散を促すため国への返還額を減額して厚生年金保険料で穴埋めする減額措置特例措置の厚労省案には、公平性の観点から、モラルハザードは避けるべきだとし、講ずるべきではなく、母体企業が負担すべきだとしている。 又、委員会では、中小向け年金制度の創設についても議論が深まっていない。 ◇ AIJ投資顧問による年金消失問題がきっかけとなり、その後も株式市場の低迷が長引き、運用難から財政悪化で深刻な問題となっている厚生年金基金制度について厚労省は、制度の改革案について骨子を2012年10月27日に明らかにした。 |
法案が来年中に成立・施行されると廃止は23年となる。その間、解散、他の企業年金制度への移行を促す。母体企業では払いきれない積立不足額は厚生年金保険料で穴埋めするという。
そうなると自己責任原則の企業年金制度の根幹を崩し、厚年基金とは関係のない被保険者の保険料を使うことになり公平性にも欠けることになる。(穴埋めの原資となるのは厚生年金の積立金)、税金の投入にも国民の理解が得られない。
但し、半数の基金は、自助努力で不足解消を図ってきており、積立不足のない健全な基金や企業年金連合会は厚労省の廃止案に強く反発している。
更に、存続を主張する政党もあり今後の調整は簡単ではなさそうに思われる。
企業年金を作る資力に乏しい中小企業の受け皿になるような新たな年金制度の整備も課題となってくる。 解散後は、DB、DCに移行する選択肢もあるが、新たな年金制度の整備も課題となってくる。(2012/10/28)
※厚労省は当初の方針を変更して一律廃止に反発する健全な基金や一部の政党から現行制度維持を前提とした見直し案が検討されており、政治情勢によっては当初の「廃止」方針そのものが見直される可能性がある。 十分な資産を持つ健全な基金は、例外として存続を認めることになっても健全な基金とは何かが問題となる。(2012/10/29)
厚生年金基金のリスク(損失)拡大と行き詰まリ
世界2位の透明度を誇る摩周湖 (10/05/02)
企業年金連合会の発表によると2012年3月1日現在、厚生年金基金数は581と公表されている。
その大半は同業の中小企業が集まって設立した総合型厚生年金基金である。
AIJ投資顧問が引き起こした年金資産の消失問題は、企業年金を取り巻く構造問題を浮き彫りにした。
中小・大手企業を問わず年金運営が経営に及ぼすリスクであることを強く印象づけた。
年金資産消失問題は、厚生年金基金の制度上の課題を明らかにしただけでなく、公的年金である厚生年金にまで被害が拡大する懸念が大である。厚生年金基金は企業年金ではあるが、厚生年金の一部(代行部分)を国に代わって運用している。
AIJに運用を任せた基金の多くは中小企業の同業が集まって設立した総合型基金である。
AIJは、受託者として忠実義務と善管注意義務をもって年金資産の運用に受託者責任を果たす信認を得て、信託財産の運用に対する裁量権を委ねられていた筈だ。 (金融商品取引法に規定されている)
基金の上乗せ給付だけでなく、その公的年金の積立金にまで穴が空いた。10年の分割払いで公的年金を穴埋めすると国に約束して解散した基金が既に29基金ある。年金倒産も14社出ている。
一部の報道によると、AIJに委ねた資産が消えれれば、52基金の積立金から上乗せ給付分が消え、加入者約33万人への公的年金も約2100億円不足するという。
厚生年金基金制度は、昭和41年の創設以来多くの基金が設立され、多数の加入員を数え、国民の老後保障制度として定着していた。基金の資産も数十兆円に達し、金融・資本市場に大きな影響を及ぼしてきた。
当時の運用利回りは年7~8%と公的年金の想定利回り5.5%を上回っていた。代行部分の運用益だけで、労使の負担なしで企業年金を上乗せできた。
バブル期、運用受託を望んだ信託銀行などが各地の業界団体に総合型の基金設立を働き掛け、政府も厚生年金の認可基準を緩めたため設立ラッシュが続いた。

その後のバブル崩壊で運用が悪化し、積立金は上乗せ給付分にとどまらず代行部分にも穴があき、企業は穴埋め負担を迫られた。
2002年、国は代行返上を認め、大企業の厚年基金は穴埋め負担して脱出した。
基金が解散するには、①代議員定数の4分の3以上の多数が議決したとき ②基金の事業の継続が不能になったとき ③厚労大臣が解散命令を出したとき・・・など母体企業の経営状況が債務超過の状態が続く見込みであるなど著しく悪化していること、加入員の減少・高齢化等により掛け金の著しい減少が見込まれ、掛け金負担が困難であると見込まれること・・・・・・・・・など
行き詰まった状況となっている基金でも、解散することもできず、更なる運用悪化を招き、高リスク投資に傾斜していった。
厚生年金基金は、特定の集団が自らの損得勘定で厚生年金本体から離脱し、代行メリットを追求したもので、その自己責任は重い。企業間相互扶助から離脱したことにより、基金を設立していない事業所の加入者にその分余分な負担もあったかと思われる。
しかし、基金が破綻した場合、代行部分をどう穴埋めするのか、いつまでもこのまま放置はできない。
基金加入の従業員も同じように保険料負担を続けてきている。加入企業の財産差し押さえ、、債権放棄による破綻処理によらざるを得ないと主張する識者もおられる。その場合、連鎖倒産の可能性は高い。
急ぐべき課題は、厚年基金の代行返上、自主的解散をより容易にする必要がある。運用利回りも厚生年金本体の実績に合わせる必要がある。
給付減額には、年金受給者の3分の2以上の同意が必要である。現役負担が増大し、母体企業の弱体化を防ぐためにもOBの給付減額は避けられない。条件緩和して給付減額の調整を図れるようにするべきだ。 |
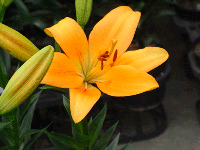 |
企業年金、国年基金とも予定利率の引き下げ、給付減額を受給者にも適用しなければ制度を維持できない状況になっていると思われる。
日本の公的年金は、「世代間の仕送り」で、賦課方式の運用といわれるが、当初は積立方式を想定していた。つまり、積立方式で始まったはずの年金制度が、途中から賦課方式と説明されるようになった。
現実に、厚生年金、国民年金ともに巨額の積立金が存在する。このこと自体がかっては積立方式が想定されていた証拠である。
厚年基金や国年基金はいずれも積立方式の年金といえる。DC(確定拠出年金)も積立型の年金である。
DCの半数以上が元本割れの状況といわれている。つまり、積立方式の年金は投資リスクやインフレにも弱い。
他方、賦課方式の年金は、現役の人から保険料を徴収し、現在の高齢者に年金を給付する仕組みである。数年間で収支が均衡するように制度が設計される。高齢化と少子化により年金財政は逼迫する。
これに対応するには支給開始年齢の引き上げ、保険料の引き上げ、給付水準の引き下げなどが必要となる。
2 DC(確定拠出年金)関係
「年金確保支援法」(2011年8月4日成立、8月10日公布) |
 |
2004年10月及び2010年1月の制度改正
| ① | DC拠出限度額の引き上げ 企業型年金、個人型年金それぞれ1人当たりの拠出限度額が2004年10月に引上げられた。 |
||||||||||||||||||||||||
| ② | 他の年金制度から企業型年金への制度移行時における過去分積立資産の移管限度額が撤廃された。これによりDBからDCへの移行に関するハードルは低くなったが、将来分の移行に関しては拠出限度額があり全面的な制度移行にはなっていない。 | ||||||||||||||||||||||||
| ③ | 積立資産の中途引出し要件の緩和 転退職後、DCへの拠出ができない者(第3号被保険等)については、加入期間3年以下の場合に加えて、資産額が50万円以下の場合にも中途引出しが認められるようになった。 (2005年10月より) |
||||||||||||||||||||||||
| ④ | DC拠出限度額の引上げ・・・・・2010年1月実施
|
老後保障が手薄になるなるのを回避するため、厚労省では次のような企業年金の拡充策も検討している |
 桜が咲いた東京スカイツリー 2012/04/13 墨田公園 |

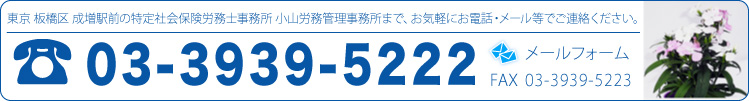

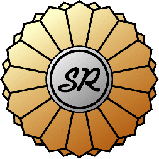
.jpg)
JAPHIC.jpg)
.png) お問合わせはこちら
お問合わせはこちら